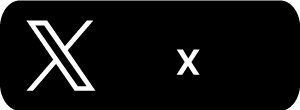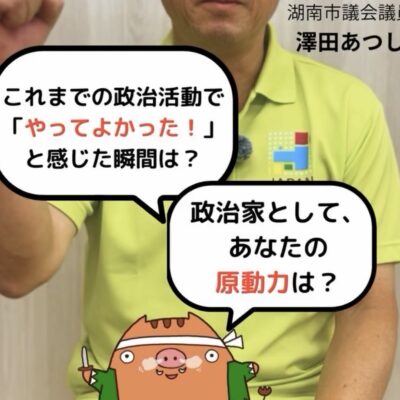このページは、市長定例記者会見の内容を秘書広報課でまとめたものです。
【市長会見事項および資料提供】
記者会見内容 (PDFファイル: 33.6KB)
司会:それでは皆様、定刻となりましたので、令和7年2月の湖南市市長定例記者会見を始めさせていただきます。本日の案件はございません。市長のあいさつが終わりましたら質問の方に移らせていただきたいと考えております。それでは市長、よろしくお願いします。
市長:皆さんこんにちは。お集まりいただきましてありがとうございます。1月の24日、25日、26日と湖南市タウンミーティングを開催させていただきました。湖南市の資源と強みを生かした3つのビジョンと12のゴールということで、このことについて、市民の皆さんと語り合うというか、そういった形で動員は一切かけませんでした。一体どれぐらいの方が来てくださるかっていうこと思っていたんですが、延べ90名の方に来ていただきまして、5つのテーマでグループ協議をしていただきました。本当に湖南市を良くするための意見というのを一つひとつ見させていただいて、これから私も皆さんと一緒に頑張っていこうという思いを新たにしたところです。また、1月の26日には、生田前市長とのお別れの会ということで、法人さんの方が主催されました。大変たくさんの方に送っていただいて、生田前市長のお人柄といいますか、本当にご家族にも愛され、市民さんにも愛され、大きな功績を残されたこと、改めて思わせていただきました。そんなことで、本日の定例記者会見ということで、どうぞよろしくお願いいたします。
司会:最初に来年度予算などのご説明をさせていただきますのは、次回2月19日の記者会見でさせていただきます。また、本日の市長定例記者会見でございますけれども、市長が次の公務の方が入っておりまして、11時40分ぐらいを目途に終わらせていただければと考えております。それでは早速ではございますけれども、市長へのご質問がございましたら承ります。何かございますでしょうか。
記者A:いくつかあるんですけれども、順に聞いていこうかと思います。今あいさつにもありましたタウンミーティングで多くの人が来たという話がありました。庁舎の関係で若い人に呼びかけて、これも意外と結構人が来たみたいな話もありまして、今回のタウンミーティングはそういう区分というか、若い人向けというわけではなかったんですよね。市長のFacebookで書いてあったかな、普段なかなか来ない人が結構来たというのが、やっぱり若者に区切ってやることが来やすかったというようなことがあったと思います。市政に対して若い人が参加してもらうというのは、大変よろしいことだと思いますので、今後もそのように進めていったらどうかと思うんですけれどもどうでしょうか。
市長:12月18日に開催しましたタウンミーティングにつきましては、18歳から49歳の方に限定させていただきました。これについては、庁舎の問題のアンケートだとか、それから昨年と一昨年、タウンミーティングに来てくださる方だとか、そういったメンバーを見させていただくと、どうしても50歳以上の方でアンケートを出しても、やはり回収率が、18歳から49歳の方が、大体20%以上落ちているということで、この年代に限定してタウンミーティングをまずやりました。「なんで今までタウンミーティングに来てくれなかったのか」と聞きますとね、やっぱり一方的に話してそれに対して意見を言われるとどうしても、何となくタウンミーティングって何か説明会とかそういったイメージがあって、「行っても自分の話って聞いてもらえへんでしょ」みたいなことをおっしゃる方が複数おられました。ですのでこうやって、年代を限定して呼んでもらうと。なかなか自分から行こうっていう感じじゃないんだけれども、呼んでもらうと行きやすいということの声を聞きました。それで、タウンミーティングのあり方については、今言いました3日間についてはそれこそ来てくださいっていう人を、何も限定はしませんでしたけれど、今回限定したのは、とにかく場所はここ、日時の設定を平日の昼と夜、休日の昼と夜、これは1つこだわりました。そしてまた保育もできますよっていうこともこだわったというか。ですので、今後タウンミーティングのやり方はいろんなパターンがあると思うんです。年齢に限定してもいいですし、場所をいろいろ工夫してもいいですし、日時を限定してもいいですし、テーマを1つ決めてもいいですし、いろんなやり方をしていきたいなと思っています。以上です。
司会:次のご質問を承ります。他にございますでしょうか。
記者B:今のタウンミーティングの関係で、若者対象の庁舎タウンミーティングを私も取材させていただいたんですけれども、ほとんど新しくなったらいいなという意見が大勢を占めていたと思うんですが、改めてそれを市長ご覧になってどのように受け止められたか教えていただけますか。
市長:はい。若者の意見、今までのアンケート、タウンミーティングに出てくださった方、パブリックコメント、そして先日答申をいただいた、そういったことも全部踏まえて、今度3月議会の方に考えを示したいなと思っています。
司会:他ございますでしょうか。
記者C:話変わるんですけれども、埼玉県八潮市であった崩落事故というものがございまして、各自治体でインフラの方がいろいろと老朽化するということでチェック体制、今後予算を上げられるかも知れませんけれども、何か湖南市の方で事故を受けてやってらっしゃる対策であるとか会議であるとか、もしやっていることがございましたら教えていただけますでしょうか。
総合政策部長:大きな陥没事故、4メートル75センチでしたでしょうか。硫化水素などいろんな部分が原因で管が割れたというな形でございます。あれは40年ほど前に施工されたというような形で、この辺りで言いますと下水道の部分につきまして、敷設ができたのが平成の始めぐらいから敷設がされてきているところでございます。先日の総合政策会議の中でも少し話をしたんですけれども、特にそのようなことは今現在はやっていないような形です。ただ、今後下水道管が敷設されて30年以上経ってきておりますので、県の指導のもと様々な関係者のもとにおきまして、調査等しっかりやっていかなければならないと思っているところでございます。特に現在のところはしていないという形です。以上です。
記者C:定期的な検査だけということでしょうか。
総合政策部長:そうですね。定期的な検査はしておるところでございます。
市長:私もですね、自分の住んでいるところの下水道っていうのが、感覚としては20年ほど前だったかなと思っていたのですが、湖南市の下水道については、昭和55年2月から供用開始で下水道44年経っていると。ですので本当に老朽化とか更新対策、これについては計画というところで、例えば上水道でしたら「湖南市水道事業施設更新計画」、これが来年度見直し。そしてまた下水道については「湖南市公共下水道事業 湖南市下水道ストックマネジメント基本計画」だとか「湖南市下水道総合地震対策計画」だとかそういったところについて、今一度本当に報道されている様子とか、ニュースとかを見ていますと、他人ごとではないということを改めて感じました。
司会:他ございますでしょうか。
記者A:文化財の事について伺います。この間書きましたけれども、湖南三山の一つ常楽寺が重要文化財の絵画を2億800万円で文化庁に売りました。理由としては、本堂を直さなければならないということがあります。話を聞いていると、屋根には3000万円以上は少なくとも用意しなければならなくて、それはそれとして放水銃を直さなきゃならないんだとか、泥棒除けのセンサーをつけなきゃならないだとか、建物のあるところで高い木を撤去しようと思ったら何百万もかかるだとか、すごいお金がかかるという話でした。本堂については、補助が市からもありますけれども、それもなかなか十分じゃないというところで、維持が難しいという話があります。それで聞きますが、市として補助とか出していますけれども、湖南三山として、観光としても大事にしているお寺でもありますので、基金とか作って何かあった時に活用するような、何らかの形で使えるんじゃなかろうかと思いますので、特に文化財で言うんだったら絵画の方も直さなきゃならないみたいなことも当然出てくると思いますので、そういう事も考えていったらどうかなと思うんですけどもいかがでしょうか。
市長:このことについても、私なりに調べてはみたんですけれども、湖南三山どのお寺も何かを守るためには、やっぱり何かを犠牲にしないといけないという維持管理費、修繕費というところで、常楽寺さんも苦渋の決断をされたというところを感じました。それこそ昔は材木を売り払って捻出されていたとか、寺の収益、これが拝観料が中心であるというところで、私たちもまず1つは、観光の充実というところは進めていかないといけないと思うんですが、湖南三山だけではなかなかリピーターは来てくださるかなと思うんですけれども、広がりというところで、1つは進めていきたいなと思いますのは、12月議会にも出ていましたけれど、やはり湖南市っていうのはものづくりのまちである、工業のまちである、そういったところで、工業団地協会、工業会にも協力をしてもらいながら、そういったところの組み合わせ、例えばお寺だけじゃなくって工場見学とかそういったところができないかなと。それが1つです。そしてまた、基金を積むっていう考えがありますかということなんですけれども、大規模な建築物の改修の場合、滋賀県と連携して国庫補助、これの要望を上げているために、計画的な予算措置がとられていると。上限1000万円ではありますけれども、だけども数年前から予算措置検討ができているので、基金を積むという考えは今のところ持っていません。非常に厳しい状況であるということは理解をしております。
記者A:湖南三山それぞれ国宝持っていますので大きそうですけれど、個人経営の問題でなかなかお金の工面が難しいと。昔はどこのお寺も山を持っていますので、木を売ってそれをお金に換えたんですけども、そういうことがなかなかできなくなったということで、行政としても何らかの手だては考えていかなければならないと思います。次にいきますが、観光の話が出てきましたので、常楽寺さんとお話しましたけれども、やっぱりそのお金がないんで全部手づくりでやっていると、どうしても見栄えが良くないのでSNSとかで揶揄されたりするようなこともあるといいます。市長も今言いましたけれども、リピーターということを考えると、計画的というかお金を突っ込んでやんなきゃならない。あるいはある程度の企画力を持ってなきゃならないというのもあります。一方で、お寺はあくまでご住職が専任の方がやっておられるので、なかなか観光をどうしていったらいいのかっていうのを考えるのは難しいのかなというのがあります、お金の面も含めて。直接市が支援っていうのはお金の面で難しいと思うんですけれども、観光協会などを通して助言とかはできると思いますから、そういったこともやっていった方がいいのではなかろうかと思いますけれども、そこはどうでしょうか。
市長:はい、本当に観光協会さんのアイデアも大事ですし、私たち自身もどういうふうにPRしていくかっていうことで、私も今、湖南市YouTube公式チャンネルでちょっとずつやっていますので、できる限りのPRは進めていきたいと考えています。
記者A:どうやったらいいか分からないっていうのがおそらくあるのではないかと思うんですけれども、お寺だけで考えることはちょっと難しいのではなかろうかという印象を受けました。境内を見ていても雑然としているところもあったりするので、その辺を上手いことアドバイスしたりだとか色々な形で支援したりだとかということをしていかないとリピーターに繋がらないかなと思うんですけども、その点どうでしょうか。
市長:アイデアっていうところですよね。これも例えば、先ほどタウンミーティングの話も出ていましたけれど、そういったことのアイデアをもらうっていうのも1つの方法かなと思っています。なにせ私たちの頭の中では、紅葉綺麗だな、立派な本堂もあるなっていうところで留まってしまいがちなんですけれども、それをどのように生かすか、三山があるっていう面を線で繋いでもらったっていうのは、元市長の素晴らしいやり方だと思うんです。そこからどう発展させるか。こういったところで、今は、そのお寺に行って美しいなというところで終わってるんですけれども、それをどう生かすかっていうところはこれからです。
司会:他、質問ございますでしょうか。どうぞ。
記者A:これが最後ですが、月曜日掲載で例の浄苑での不祥事について、市の方が若手職員さんのスマホ内の画像の削除を確認しなかったということを書きました。いくつか問題があるかと思っています。他の自治体に聞きましたところ、普通はするだろうということがありました。プライバシーに配慮したと言うことですけれども、そもそもそういうものを持っている事自体がよろしくない事だということがあります。大学の先生に聞きましたが、大学の先生の言い方では市のミスであると、こんなことは。場合によってはそういう風にやったことを処分しても良いというようなことも言っていました。質問はここからですけれども、そういう市のミスでもあるというふうなことの話で、これをこの前指摘しましたが、ここをきちんとやっておけば、2回目の処分というのはもしかすると無かったあるいは虚偽報告ぐらいで済んでいた可能性があります。という意味では、今回の処分はやっぱり無理があったのではなかろうかと思うんですけれども、そこはどうでしょうか。
副市長:はい、お答えします。まず、今回の処分に関してですけれども、前回も申し上げておりますけども、顧問弁護士の方には確認をさせていただいています。というのは、当初虚偽ということでの処分の整理で考えておりました。あわせて前の処分を取り消して改めて処分できないかということを調べておりました。そうしたところ、国家公務員法上そういう対応がとり得るのではないかということで、そうであれば、地方公務員法上も同様の考えではないのかということで、人事課に確認の指示をして、私個人としては県にも確認をさせていただいたと。県の回答としては事例が無く具体の回答は困難であるけれどということ。その上で、様々な確認をしたが、処分の取り消しにかかる内容は見当たらないと。弁護士にまさに相談すべき事案ではないかということでありました。こうした中で、人事課から顧問弁護士の回答の報告がございました。処分の取り消しについては困難と考えられるものの、新たに判明した漏洩行為も含めて処分対象とすることは可能ということでございました。なお、このことについては7月にもですね、人事課から確認をしてくれておりまして、その際にも処分対象に含めることは可能という回答でございます。こうしたことから、そこも含めて量定検討をしたということでございます。
記者A:質問の趣旨はちょっと違ったんですけど、そこら辺も聞こうと思っていたので、答えていただいた所から聞きます。顧問弁護士に確認したと、前回取り消しでその上でということはなかなかできないという話でしたが、総務省に聞いたところ、確かに原則はできないと。これは最高裁の判例があるそうです。一方で、例外的にできるケースがあると。
著しく処分の内容がいわゆる誤っている、あるいは考え方が違っているっていうようなところであるんだったらそれは可能である。それは、行政実例に載っているらしいです。今回の場合であればそもそも1回目の処分が秘密漏洩に準じるという形で処分していますので、後からこれが秘密漏洩に変わりましたということでやるんだったら1回目の処分については当然考え直さなければならないんですよ。停職6ヶ月と減給6ヶ月っていうのはかなり大きな開きがあるということで、まずそこを考えなければならないのではなかろうかと思うんですけれども、そこはどうでしょうか。
副市長:そこも含めまして処分の取り消しについて考えていったということであります。その中において、県にも確認し、顧問弁護士にも確認したという流れであります。顧問弁護士の回答として、新たに発覚した漏洩も含めて処分することが可能ということでありますから、そこも含めて量定を検討したということであります。
記者A:新たな部分については、それは処分ができるということです。大学の先生の見解もそうですし、総務省の見解もそうでした。それはいいんですが、要するに処分の基準が違うんですね、これ。1回目と2回目で。これは大学の先生の言い方でいうと公平性公正性に欠けるということであります。であるんだったら、全体的に処分のあり方を補正するということが必要ではないかと、そういう問いかけの記事なんですけれども、そこはいかがでしょうか。
副市長:繰り返しになりますけども、何で処分の取り消しということができないかということを考えたということであります。
記者A:今聞いた中では、県に聞いたと顧問弁護士に聞いたと。前回も言いましたけど、顧問弁護士がどの程度能力あるのかっていうのはかなり前から私は疑問に思っていますが、そもそも県の上で法律について所管している総務省がそうやってできると言っております。それははっきり言ってここも含めて市もきちんと確認すべきだったと思うんですけれども、これも含めて市のミスだったんじゃないですか。
副市長:総務省には確認を取っておりません。
記者A:当たり前ですけれども、県の見解と総務省の見解であるんだったら、総務省の見解の方で検討すべきだというふうに私は思うんですけれどもそこはいかがでしょうか。
副市長:ご意見としては受け止めておきます。
記者A:話を最初に戻しまして、要するに画像の削除について確認をしなかったと。これは大きなミスではないかというようなことであります。これさえやっておけば、3人目の人に画像を送っただとか再送しただとか、場合によってはしつこく話を聞いていたら虚偽であったことを最初のうちに分かったかもしれないということがあります。私も取材で場合によっては何度も何度も対象者に聞きます。その中で新しい事実が出てくるようなことも当然あります。という意味では、そもそも市のやり方がまずかったから2回目の処分に至ったと私は思いますが、そこはいかがでしょう。
副市長:まず被処分者自体は、保身のために事実を明らかにしなかった、嘘をついていたということであります。後からですね、新たな事実が判明したということであって、調査過程でできることがあったのではないかと捉えるべきと考えております。結果的にではありますけれども、例えば本人の了承を得て確認をする、あるいはその上で関係のないものについては別フォルダに移動してもらった上で、本人の了承を得ながら確認をするということが考えられたのではないかとは考えております。隠しているかも知れない、あるいは本人の話を鵜呑みにし過ぎたという面はあると考えております。
記者A:分かりました。それでですね、最初に送った2人のうちの1人に再送したというのが2回目の処分の事由にありました。これは二重処分に当たる可能性、二重処分にあたるだろうということを大学の先生が言っております。事実として提示するのはすべきだと思いますが、それを処分理由に入れるというのは不適当ではなかろうかと思うんですけど、ここはどうでしょうか。
副市長:顧問弁護士に相談した結果でこれは判断をしておりますので、そういうことであります。
記者A:顧問弁護士に聞くのはよくわかるんですけれども、そもそもこれに限らず、何度も言っておりますが、弁護士というのはですね、クライアントの意向を最大限に尊重して考えるというものであります。その上で顧問弁護士は、ここ何年か同じ顧問弁護士事務所ですけれども、その法的な理解が本当に大丈夫なのかと。これ具体的な事を言うのは避けますが、長くなりますので。これを考えた時に、顧問弁護士に聞くのは良いでしょう。でも、絶対的に考えるのはよろしくなくて、やっぱりきちんと総務省に話を聞いたりだとかするべきだと思うんですけれども、そこはどうなんでしょうか。
副市長:法的な解釈に関して疑義が生じた時に、そこの助言を得るために顧問契約していると考えておりますので、顧問契約をしている弁護士に相談し助言を得るというのは、間違っていない行為であると考えております。
記者A:だから二重処分には当たらないと。弁護士さんの言う事を信じているということの理解でよろしいでしょうか。
副市長:はい。
記者A:わかりました。
司会:他、質問ございますでしょうか。
総合政策部長:下水道の資料を確認しましたので報告させてもらってよろしいでしょうか。
上下水道課からの資料で、下水道管の管路の施設に対する緊急点検というのが出ているところでございます。それにつきましては、管の口径が、2000ミリメートル以上の下水管の管路、直径が2メートルですね。それ以上の管路の口径、また晴天時には1日最大処理量300,000立米以上の大規模な下水処理場に接続する口径の部分の緊急点検が出ておりまして、近畿圏内確認させていただくと5ヶ所出ているような形でございます。大阪府3ヶ所、奈良県、兵庫県が1ヶ所というような形でございますので、滋賀県については緊急点検というのはございませんが、5年に1度の法定点検、また、ストックマネジメント計画に基づく点検、日常の維持管理については適切に実施してくださいという形でございます。以上でございます。
記者A:処分の話の続きなんですけれども、行政っていうのは基本的に前例踏襲主義でありますので、1回目の処分が秘密漏洩に当たるかどうか分からないから準じるという形にしたと。ところが、秘密漏洩であったということで、本来だったらここは絶対に補正しなきゃならないと思うんですけれども。先々の行政にですね、湖南市の行政に関わってくると思うんですけども、ここは補正しないのでしょうか。要するに、秘密漏洩に準じるという形での処分でした。実際は秘密漏洩だった。だからここで少なくとも処分のあり方は変えなきゃならないと。取り消すという形にするのか、まとめるという形にするのか分かりませんが、その1回目を間違えた秘密漏洩だった訳なんですから、これを停職6か月という形にすることにしないと、後々問題になるかと思うんですけれども、それはやらないのでしょうか。
副市長:そこも含めて、顧問弁護士に確認した結果であるということであります。
記者A:いや、要するにやらないってことなんですかね。総務省の見解、行政実例だと判断が間違ってたということである場合は、取り消し、あるいは変更は可能だというふうになっております。顧問弁護士がどこを調べて、どこの何を調べて物を言っているかわかりませんが、少なくともそういうふうに行政実例にある以上、総務省もそういう見解を出している以上は検討に値すると思いますが、そこはいかがでしょう。
副市長:もう1回調べてみたいと思います。
司会:他ございませんか。
記者D:すみません、19日の予算の記者会見ですけれども、あれはその日解禁ですか。
総務部長:はい。
司会:他よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは2月度の市長定例記者会見の方を閉じさせていただきたいと思います。冒頭にも申し上げましたけれども、次回の定例記者会見は2月の19日の水曜日、変則の開催となっております。水曜日の午前11時からここ大会議室の方で開催させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 秘書広報課
電話番号:0748-71-2314
ファックス:0748-72-1467
メールフォームでのお問い合わせ
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。