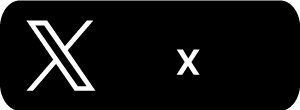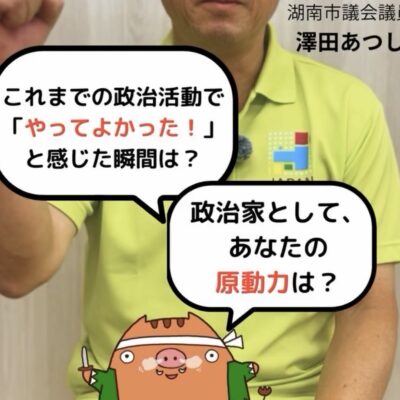このページは、市長定例記者会見の内容を秘書広報課でまとめたものです。
【市長会見事項および資料提供】
記者会見内容 (PDFファイル: 31.1KB)
司会:それでは定刻となりましたので、令和7年10月度の市長定例記者会見を始めさせていただきます。
はじめに、本日のスケジュールですが、市からの資料提供はございません。
このあと、市長からごあいさつをいたしました後に、皆様にその他のご質問を承ります。
市長よろしくお願いします。
市長:皆様こんにちは。
お集まりいただきまして、ありがとうございます。
明日、閉会式を迎える、わたSHIGA輝く国スポにつきましては、9月29日、30日、そして10月1日と、剣道競技を湖南市総合体育館で、無事に終えることができました。
選手の皆様の健闘が、剣道競技滋賀県チームの総合優勝につながりました。滋賀県剣道連盟の長年に渡るご尽力が実を結んだものと喜んでおります。また、「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」を盛り上げるために、そして、全国からお越しくださった皆様をおもてなしするために、協賛企業をはじめ市民の皆様には、大きなご支援をいただきましたこと、心から感謝しています。
取材にもお越しいただき、ありがとうございました。
続く、障スポは、今月25日土曜日、26日日曜日に、同じく湖南市総合体育館にて、バレーボール知的障がいの部が開催されます。国スポ同様に、選手や応援に来てくださる皆様をお迎えしたいと考えております。それではよろしくお願いします。
司会:それでは、その他ご質問等承りたいと思います。何かご質問ございますでしょうか。どうぞ。
記者A:本日付の新聞でも、ちょっと書かせていただいたんですが、まちの課題と争点、これですね、庁舎整備の対応ということで、3つほど、質問をさせていただきたいんです。
松浦市政としては、生田市政の継続ということを掲げられて、今回就任をされたということなんですけども、今年のですね、今回の9月議会で、冒頭に庁舎の南側に、建て替え表明された。
これはある種の施策の修正というふうに、ちょっと受けとめたんですけれども、それに関してですね、A案、B案、C案とあったんですが、それの中で、まずですね、谷畑市政のときの計画と何が違うのかというのが1点です。
あともう1つ、これ私も情報公開請求したんですけれども、消防署がですね、計画についてですね、これ今どういう状況なってるのかということですよね。これはやっぱり今の建て替えの方針もどう関係あるのかということです。
3つ目なんですけれども、やはりですね建て替えということになってですね、市政がちょっと、何回か転換をしてるわけなんですけれども、やはり資材の高騰と、それから人件費ということもありまして、かなり数十億円というふうな費用が余計にかかるということで、この間の決定に関わるということに関してですね、第三者委員会での検証が必要とされるのではないかという指摘があるんですけど、これについて、将来的にその第三者委員会の設置についてのお考えはありますでしょうか。以上です。
市長:ご質問ありがとうございます。
まず1点目なんですけれども、1点目の前の方ですけれども、それこそ、生田前市長の方針から一転しているんじゃないかという、1つのご質問だと思うんです。これについては、一転というわけではございません。というのは、生田前市長は、庁舎に必要な機能を吟味し、全面建て替えだけでなく、現庁舎の耐震補強と増築による庁舎整備も視野に入れ、より効果的、経済的な整備方法について、再考するとされました。その中で、谷畑元市長時代の耐震2次診断では、Is値0.52でありましたが、3次診断、これを実施されて、その結果、Is値0.22という、危険であるという、数値が出ました。ですが、生田前市長は、最終決定までは明言されていないっていうことですので、何かこう、決定されたことを一転したということではないという、これが1つ目、前段です。
もう1つ、南側建て替え施策の修正、このことですね、谷畑元市長の計画と何が違うのかということなんですけれども、このことについては、様々な面で、議論をしまして、それも、庁舎整備については庁舎整備検討特別委員会も設置をされましたので、その中でも、報告等もさせていただいてるんですが、今の場所になぜ決めたのかっていうことなんですけども、1つは、まず新庁舎への移転時期、これが先ほどの0.22という数値も出ておりますので、防災拠点の整備は、1日も早くということこれが1つ。
そして、もう1つは財源計画、令和8年度までに、建設工事着工で集約化とか、複合化の事業債の適用がこれが可能であると、ですから、早くというところ、このことが交付税措置で5.9億円の差があるということと。それから、物価高騰のリスク、これもどんどん上がっています、それこそ、国土交通省の試算によれば年4%。ですから、年4%ということは上がっていますっていうことなんです。
そして、1つはA案、B案、C案あった中で、環境負荷への対応。
それから、もう1つは、一番このことが新しく打ち出せたかなと思いますのは、東庁舎周辺施設を一体的なものとして考えようと、玄関の方向を今の甲西図書館の方に向けまして、甲西図書館、甲西文化ホール、そして森北公園、この周辺も一体的な、憩い文化ゾーンとして考えるという、ここが1つ、私になっての考えかなと思っています。
そして、もう1つ早くというのは、新庁舎の施工性と既存施設の利活用ということで、このことについては、もう1つの質問とも重なりますけれども、消防署、それから社会福祉センターの除却というのは、新庁舎建設の「必ず」の条件にはならないというところであります。ですので、先ほど、ご質問いただいた谷畑市政の時の計画と何が違うのかという中で、急ぐということと、それから、一体的に考えたい憩い文化ゾーンがあるということ。このことを推していきたいなっと、思っています。
そして、ご質問がありました消防署の状況ですけれども、これにつきましては、甲賀広域行政組合で、今年の3月に策定した、湖南中央消防署整備基本計画に基づいて、建設敷地の取得に湖南市で取り組んでいるところであります。
甲賀広域行政組合と共に、住民説明会で候補地について説明はさせていただきましたが、現候補地については、大変厳しいご意見をいただいているところであると、現時点ではそのように、回答させていただきます。
それから、数十億円の差っていうことなんですけれども、このことについては、やっぱりもうタラレバの話になりますので、それこそ、新型コロナウイルス感染症対策優先のために、令和2年6月に一旦見送りをしています。
そして、そこからも、どんどん物価の高騰もあったりする中で、本体の建設工事費も、それなりに、あがっています。
そういったことについて、今、第三者委員会というお話も出ましたけれども、その考えは持ってはいません。議会の特別委員会等で報告、それから、ご意見をいただいたりする中で、進めてきていますのでというお答えです。以上です。
記者A:ありがとうございます。すいません、ちょっと再質問になるんですが、谷畑市政と何が違うかと言うと、スピード感ということだと、もう1つは施設、また、再利用するというか、一体化して使うということですね。
スピード感ってのは、多分どの市政においても、多分一緒だと思うんですよ。なので、これだけ計画遅れていて、このスピード感っていうのはちょっと、私としてはちょっと、もう1つ何か、強い要素が、とはちょっと思われるのと。
あと、もう1つ一体的なというのがですね、ちょっと、これもちょっと要素として、ちょっとどうなのかなということで、あともう1つは詳しめに、ちょっとお話で、ちょっと個別にお伺いできたらなと思ってます。
いろいろと現立場として、お伺いしたいなと思います。
それと、消防署の方なんですけれども、やっぱりこれはですね、現計画南側駐車場ってのはですね、これ、やっぱりよく読んでますと、浸水リスクってのはあるんですよね。浸水リスクっていうのがあって、それも含めて勘案したんですけれども、それで高台からなぜ下ろしたのかという。ちょっとなかなか、意地の悪い言い方をすればですね、この消防署の方が、なかなか進まないというふうな、頓挫してるような状況のように読めるんですよね。説明会資料、これ6月の6日なんですけれども。なかなか、どうもうまくいってないというふうな受け止めなんですけれども、この資料を読む限り。これとの関わりっていうのが、ちょっと、何となく、どうなのかなというふうな、ちょっと関係があるのかなというところです。
今市長ね、関係ないって、おっしゃっていましたけれども、その辺りのことはもうちょっと時間をかけて、お話を、この場ではなくて、一つ私の視点として、じっくり取材をしていきたいなというふうに思っております。
あと3番目の第三者委員会の設置のつもりはないというふうなことだと思うんですけれども、とにかく前に進めなくちゃいけないということはそれはよくわかるんですけれども、だからこそですね、やっぱりその検証というのは、必要なことでですね、これは今必要でないというふうなことなんですけど、実はこれ理事者だけじゃなくてですね、市議会の方もきちっと、議論をしていない。前回の市議会の報道で、松浦市長からその南側駐車場で建て替えるという方針は、表明をされた、表明して、あとですね、これが一般質問でも、或いは本会議でも議論が行われていない。よく聞けば、夏の閉会中の特別委員会でですね、説明をしたと、あとは全員協議会で説明をしたというような話になってるんですよね。普通だったら、特別委員会の方で、委員会委員長の方から委員会報告というのが、全協じゃなくて本会議の場であって、そこでお諮りしますということで、賛成討論、反対討論というのが、議長がですね、裁いて、最終的にその議決を取るという形になるのではないかというふうに、議会にも聞いてるんですけども、どうも話がかみ合っていない。
これは別に理事者の責任でも何でもないんですけれども、議会できちんと、もまれた形になってないんですよね、ですから私は理事者というよりも議会ちょっとしっかりやりなさいよ、きちんと議題として、やらなくちゃいけないことを、あなた方はやっていないのではないのかというような、市議会をですね、激励としてちょっと書かせていただきました、今回はね。
なので、市議会の方でしっかり議論されたとは思えないわけで、それを報告をしたというだけでですね、どんな意見が出たのかというふうなところは、少なくとも、本会議には傍聴した中で、ちょっとよくわからないんですけども、それをもって、第三者委員会の検証の機会をちょっと設けないっていうのは、ちょっと私としては腑に落ちないところではあります。以上です。
総務部長:A記者さんの再質問に私の方から答えさせていただきたいと思います。
まず1点目、スピード感についてでございます。A案、B案、C案それぞれスピード感はそんなに変わらないというふうに、記者さんは認識をいただいてするようですが。
記者A:いやそういうことじゃなくて、谷畑市政とどう違うんですか言うたら、まずスピードということを、上げられたらから、それはいつの市政でも一緒でしょっていうことをお伝えしただけです。
総務部長:その移転時期につきまして、A案、B案、C案ですと、やはりC案、南側駐車場に建設をするのが、一番早く工事に着工できるっていうふうに、私どもは考えました。というのは、浸水を避けようとすると、やはり、高台に設置した方がいいんですが、高台に庁舎を設けようと思いますと、既存の消防署ですとか、社会福祉センター、あちらの除却が必須となってきます。まずそちらをどけて、土地をあけてから、その土質調査、地盤の調査に入って、それから建設工事に入らなければならない。そうすると、それなりに時間を要してしまいます。しかし南側駐車場、下のところに庁舎を建設することによりまして、もともと前に行いました、実施設計を活用することができまして、その実施設計の期間も省略できますし、支障になるものがございませんので、建設工事に速やかに着工ができる。そういう利点を踏まえまして、下、南側駐車場に建設をした方が、一番移転時期が早いのではないかという結論に至ったわけでございます。
それと、2点目、検証の必要というのは、ちょっと私の方から、答えは用意させていただいてなくて、申し訳ございません。議決に関しまして、記者がおっしゃいますように、庁舎に関しては、何らかの形で、議決をいただく方が執行部としても、後々やりやすいっていうのは、私どもも認識しておりました。
ただ、議決の方法というのを、いろいろ調べてみたところが、どういった形で議決が取れるのかというのに、思い当たらなかったということです。
ここじゃなくて、もっと違う場所に移転をするならば、その場所に関する議決っていうのは当然いただかなければいけないので、ここでは議決をいただくことができたんだろうと思いますが、同じ番地、同じ敷地内で、場所をちょっと変わるだけで、そこが、その条例の改正までには至らないという判断から、議決をもらうのは難しいだろうという判断から、特別委員会で説明をさせていただいて、議員の皆様には、委員長から報告をいただいて、議会の了承を得たという形をとらせていただいたところでございます。
記者A:よろしいですか。すいません。
2点ありまして、進捗報告書を読めば全部わかります。全部書かれてます。それを、よくわかった上で質問をしています。そのうえで、要するにまず懸案事項で、今、その高台にある消防署をね、どこに移転するかというところで、まず、ちょっと見通せない状況にあるという中ですよね。これどうするんですかって、質問したんですけど、ちょっと今、納得できる回答がちょっと、まだ、いただいてなかったんで、その後でいいんですけれども、もう1つですね、議会の議決をもらった方が今やりやすいっていうふうに、今おっしゃいましたけど、これ、二元代表制ということ、まるで理解されていないんじゃないですか。賛成ができて、そんなふうに話をもっていくんですけれども、これ、通過儀礼じゃないのでね、議決は議決でしていくんですけれども、当然、反対意見ていうのは当然、出てくるんですよ。
今、要するに市民運動というのがあって、これは、その是非は言いませんけれども、この建て替えに関して、疑問視している声も出てて、それに関して立候補されてる方も複数いらっしゃるわけですよね。議決をもらった方が、あと、やりやすいっていうのは、ちょっと、すごく、聞いたことないですよね、こんなこと、ちょっとおかしいでしょう。
これ、私じゃなくて、多分他社の方も、「うん?」と思うような話なんですよね、これね。これは言ってみたら、別の立場なので、市議会と理事者っていうのは、互いに緊張関係があるわけで、二元代表制ということを、申し上げましたけれども、やってもらった方が都合がいいっていう、そちらの理事者の都合でお諮りしますっていうのは、これはとんでもない、有権者への冒涜ですよ、市議選を前にしてね、そのあたりのところがね、もっとも総務部長さんだけじゃないんですよ、これ、お話を聞いてたらどうも話がかみ合わないていうのかな。
私も、新聞記者1年生ではないんですけれど、ちょっとこの辺のところが、どうも私が今まで記者生活やってきた、いろんな行政を担当した話と、職員の方々とかみ合わないなあというふうに、いや、もう説明したからもういいですよ、この話終わったんですよ、みたいな感じで、色んなところで言われてきたんですけれども、いや、ちょっと記者さん、基本的なことをわかってますか、みたいなこと言われたりとしまして、いや、わからないから聞いてるんですっていう話で、そんな話になってるんですけれども、ちょっと今、総務部長さんのお答えに、ちょっと私は、戸惑っているなというところです。あんまり頭良くないで私もね、わからないことは一個一個聞いてるんですよね。
総務部長:私の言葉、説明がうまくなくて申し訳ございません。議決をとればやりやすいというのは、申し訳ございません。おっしゃる通りでございまして、必要なものに対して、議決をとっていくのが当然のことでございまして、今回の場合、議決をいただかなければならない事案が、私どもでは思いつかなかったところでございます。
記者A:はい。わかりました。はい、時間をかけてやっていきます。別にそれ、言葉をとって、今ね、このやりとりを、きっちりするなんてことじゃなくて、1個1個、ちょっといつになるかわからない記事なんですけれども、私も石積みを積んでいくような形で、今、パッと積んで、一個一個丁寧にやっていきたいなというふうに思っておりますので、また、取材にご協力よろしくお願いいたします。私の方から以上です。
司会:他ございますでしょうか。
記者B:すいません、ちょっと別件でお伺いいたします。松浦市長は中教審の委員を務めていらっしゃいます。ご存知かと思いますが、先月24日に、中教審の作業部会がデジタル教科書を正式な教科書として認めるとした、最終的な答申を了承しました。海外の事例を見ると、エストニアとか、米国では成果が出ていて、デジタル教科書を維持していると、一方で韓国では教育資料に格下げするとか、スウェーデンでは、紙の教科書に後退するとか学力低下というふうに認められたということで、そういった動きがあって、分かれております。
松浦市長は教育者の経験もおありで、中教審の委員も務めてらっしゃるということで、このデジタル教科書についてはどのようなご見解を持たれているでしょうか。
市長:ご質問ありがとうございます。この部会は私の属している部会ではないんですけれども、デジタル教科書か、紙の教科書か、どっちかっていう論議ではないと思うんです。それこそ、今の子どもたちにとって、デジタル教科書も必要ですし、やはり紙は紙で良さもありますし、そういったところで、どちらかっていうことではないと思いますので、今の子どもたちに即した教育をしていくなら、デジタル教科書はこれは必須でありますし、だけども、やはり紙で読んで、お互いに紙を持ち合って、共通理解するとか、議論するとか、そういったことも必要ですし、どちらかという議論ではないと、そのように考えております。
記者B:ありがとうございます。併用がよろしいんじゃないかというご見解かと思うんですけれども、デジタル教科書に切り替えるとしてもですね、現場の教員の方の対応が間に合ってない、どう使って良いかわからないということで、しっかり子どもたちに教えられないんじゃないかという現状があります。何かそのことについて、どういった対応が好ましいとか、お考えありますか。
市長:それこそ5年ぐらい前でしたら、デジタル教科書云々っていうところの導入で、教員が教えることを、本当に困るんじゃないかっていう懸念はすごく大きかったと思うんです。ところがこの1人1台端末が導入されたことによって、やはり教員自身も、学び続けておりますので、そういった懸念っていうところは、コロナの前の時期からすると、かなり軽減してると考えています。
記者B:ありがとうございます。ちょっと最後、関連で1点、デジタル教科書に、仮に完全に切り替わったとしましたら、ネット環境に繋がるわけですけれども、それが動画とかいろんなサイトを自由に検索することができると思われるんですよね。ちょっと勉強が本分ですけれども、そういった動画を見て、学力低下に繋がる恐れもあると思うんですが、その辺の対策とかは何か考えてるんでしょうか。
市長:本当にメディアリテラシーというところの、この教育っていうことを、家庭と一緒に、学校が一緒にやらないと、ここのところは学校だけで担っていても、本当に追いつきませんので、そういったところで、家庭、地域そして学校というところで、そこをしっかりと土台としてやってからでないと、やはり、繋がっていますから、全世界といろんな情報が。そういったところの教育はますます強化していかんといけないだろうなと、そのように考えます。
記者B:わかりましたありがとうございます。ちょっと追加でなんですけど、デジタル教科書の採用、今紙の教科書が法律で正式な教科書として認められてるわけですけれど、デジタル教科書が導入されると、子どもたちにとっては、例えば、英単語の音声が聞こえたりとか、理科の実験の動画を見られたりとか、そういう利便性がある一方で、ちょっと私が個人的に懸念してるのが、生成AIの台頭が今ありまして、それは中教審とか、その教育界では、今どのように生成AIを捉えられてるかっていう、松浦市長のご所見を伺えればと。
市長:私の入っている部会では生成AIの話は出ていないんですけれども、それこそね、今の教科書も、2次元コードがたくさんついてあるんですよ。あれによって、デジタル教科書っていうこともありますけれども、本当にね、いっぱい付いています。だからそれで見たら、いろんな情報がそこにありますから、教科書自体が、私たちの頃、記者さんの頃とは、教科書が本当に変わっています。驚かれると思います。
記者B:ごめんなさい。QRコード今の紙の教科書に載っているってのは私も承知しているんですけど、これデジタルになることによって、その紙の教科書、今現時点だとデジタル端末で見づらいという状況があると思うんですけど、それは導入が正式決定されると見やすくなるっていう認識ですかね。何か革命的に変わることっていうのは何か捉えてらっしゃいますか?
市長:どうなんでしょうね。私もそのデジタル教科書を使って、授業したことはもちろんないですのでね。ただ、今までも、いわゆるICTを使った授業とか、そういったこともやっていますので、ツールとしては使えるようになってきていますけれども、紙の教科書とデジタル教科書と併用っていうのか、私の今の考えではそういうことにしかたどり着いていないんですけれども、自分が実際授業したときに、どうしたら、子どもたちに伝えやすかったりそれを使ってもらえるような教科書、昔はもう教科書の知識をとにかく得るっていう授業だったと思うんです。
だけども、これからの授業は、もう教科書に書いてあることを、それを論点というか、そこからいろんな話が広がっていくような、授業をしていかないと、今までと同じように、知識を得るだけの授業では、それこそ生成AIにも、負けてしまうというのか、聞いたらいいわけですよね生成AIに。私もよく相談するんですけど、さっと答えてくれます。
だけども、それが全部本当かっていうとそうではないことやとか、やはり、自分で考えてそこから選んでいく力っていうのは、これからの教科書を使う上で非常に大切な力かなと思っています。
記者B:ありがとうございます。
今生成AIの話が出たんで、ちょっとご見解をさらに伺いたいんですけど、アメリカでですね、この生成AIにどっぷりはまってしまった子どもが、自死に至ってしまったっていう、その自死の方法を生成AIから教わってということで、そういう悲しい結末がありました。
国内の調査で、一部の調査にでも、身近な家族や恋人とか、周りの人よりも生成AIに依存しやすい、信頼を寄せてるという調査も出たりしてます。
長年、市長が教育界に携わってきた中で、子どもたちと接する中で、子どもと生成AIの関係については、どのような。
市長:そうですね、やっぱり人が人と対話できる話ができる、そのことが非常に大事だと思うんです。私、発達支援室長もしておりましたので、高校生だとかそれ以上の方からも相談を受けてたんですけれども、やはり立ち直りだとか前へ向く意欲っていうのは、例えば薬ですね、お医者さんにかかっておられて、適切な薬を使って、治るっていう、前に向けるっていう子もいるんですが、やっぱりそれよりも、定期的な面談、人としゃべると、そういう話ができる人と、いかに、めぐり合うかっていうところが非常に大事で、だけど、懸念するのはやはり生成AIってね、タイムリーに答えてくれるじゃないですか。しかも、私がよく言うのが、私の知的レベルで答えてくれるんですよ。だから、わかりやすい。
そして、決して落ち込むようなことを言わない。なので、その辺りで、これから教育界も難しくなっていくのは、いかに、人と話せる機会を持っていくかっていうところかなと思います。
記者B:わかりましたありがとうございます。
司会:他、ご質問ございますでしょうか。
副市長:先ほど記者Aさんの庁舎の関係で、ご質問いただいた補足なんですけれども、確かに議会で議案という形では出てはいないんですが、これ、庁舎整備の特別委員会、こちらの方には付託をしておりまして、一応7月30日の庁舎整備委員会の方で、これホームページに載ってるんですが、特別検討委員会の方でご議論いただきましてね。このC案が最適だと、いうようなご意見もいただいてますので、議案という形ではないんですがしっかり、執行部側としては、議会の方にもご説明してご審議いただいたということだと考えておりますし、これまでの経緯についても、やっぱりしっかり市民さんにも、説明をしなきゃいけないということで、今度の10月1日号の広報にしっかり掲載しておりますし、これまでの経緯を含めて、市としてしっかり説明をさしてもらってはいるというふうに考えてます。
記者A:それは承っております。私もそのホームページを見ておりますので、ただ、委員会でね、議決してやったんじゃなく、本会議にかけて、最終的にしないと、それでやっぱり議案としてね、やっぱその叩いてっていうふうな作業がないと、それは議会に提案したということには、私、議会が提案して議会が議決して了承したっていうふうなことには、私はならないと思う。議会の方がその辺をどう理解してんのかなというふうなところで、あれなんですけど。
普通は委員会で、ものをですね委員長が報告して、先ほど申し上げましたけど、お諮りしますと、委員会では3対5によって、3対2で一応可決しましたと。
本会議にかけたら、また別の意見が出てくるもんなんですよねというようなことを、これが普通こうじゃないですかっていうふうに、原課の方に聞いたら、記者Aさんの普通って何ですかよくわかりませんて言われて、あなたが思っている普通なんじゃないんですかって、それは、あなたの意見でしょう、某youtuberのきめ台詞なことを言われたから、何も言えなかったんですけど、俺の経験不足なんかな、僕の経験不足なんかな、僕の普通っていうのは違うのかな、いわゆる議会運営というのはそういうもんだと思ってますので、委員会でやって、そこで説明したから、一応意見が出ましたっていうんじゃなくて、やっぱり本会議っていうのは誰もが見てるところなので、そこで決をとるというのが私は、議会政治の在り方じゃないのかな、特に地方議会って、地方の首長、市長といえば、ものすごく権限が強い、議会を解散できる権限を持っているんですよ、そういう意味ではアメリカの大統領なんかよりも強力な権限を持っているんですよね。アメリカの大統領制っていうものを参考に戦後取り入れられたと私は読んでいるんですけど、トランプ大統領だって議会解散できませんから、すごい権限をもっているんですよ、だからこそ、二元代表制ってことでね、やっぱり理事者としてもね、しっかり議論せいとは理事者にはよう言えませんけどね、もっと尊重するべきではないのかな、お互いもっと緊張感をもつべきではないのかなということを申し上げたまでです。
副市長がおっしゃることはよく重々承知の上で、私も質問させていただきますので、すいません。
司会:よろしいでしょうか。それでは、これをもちまして、10月度の市長定例記者会見を閉じさせていただきます。次回は11月4日の11時を予定しております。本日はどうもありがとうございました。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 秘書広報課〔東庁舎〕
電話番号:0748-71-2314
ファックス:0748-72-1467
メールフォームでのお問い合わせ
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。